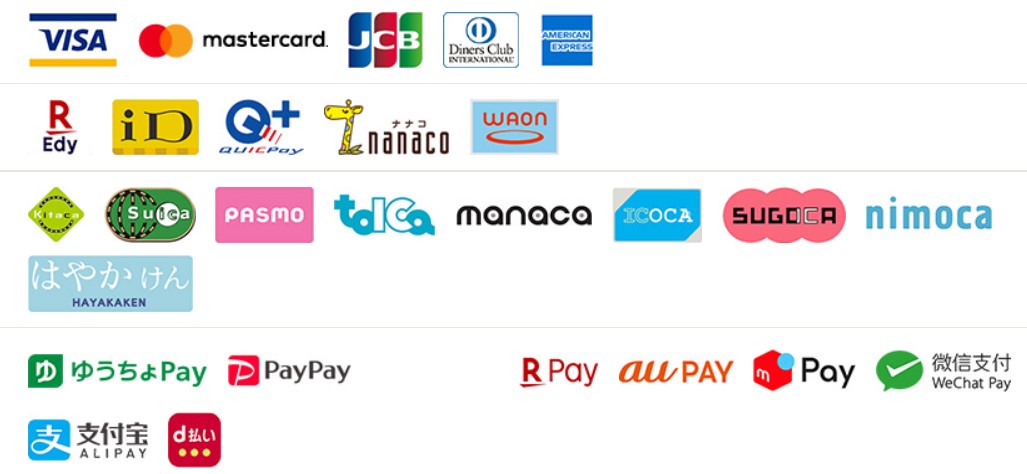下痢対応外来
💧下痢についての説明
下痢は「便が普段よりもやわらかく、水っぽくなる状態」を指します。 腸の動きが活発になりすぎたり、水分の吸収がうまくいかなくなったりすることで起こります。 一時的なものもありますが、長く続く場合や発熱・腹痛・血便を伴う場合には、 病気が原因になっていることがあります。 下痢は「急性(急に起こったもの)」と「慢性(長く続くもの)」に分けて考えることが大切です。
初診の際には可能な限り問診と診察で対応し、必要に応じて便培養検査・腹部エコー・腹部レントゲン・内視鏡検査・採血尿検査などをお勧めして対応します。
⚡ 急性の下痢(数日以内に急に始まる下痢)
急に下痢が始まり、数日〜1週間ほどで治まることが多いタイプです。 多くは感染症や食事が原因ですが、重症化することもあります。
主な原因となる病気
感染性胃腸炎(ウイルス性・細菌性) ノロウイルス、ロタウイルス サルモネラ、カンピロバクター、腸炎ビブリオ、大腸菌(O157など) 食中毒(傷んだ食品、飲料など)
抗菌薬関連下痢(抗生物質使用後の腸内細菌バランスの乱れ)
急性腸炎 急性虫垂炎・胆のう炎など、腹部臓器の炎症に伴う下痢
寄生虫感染(ジアルジアなど)
薬剤性下痢(下剤、抗生物質、糖尿病薬など):メトホルミンなど
👉 注意: 発熱・強い腹痛・血便・脱水(口の渇き、尿量減少)を伴う場合は、早めの受診が必要です。
📆 慢性的な下痢(数週間以上続く下痢)
長く続く下痢では、腸や消化吸収の病気、内分泌異常、薬、ストレスなどが関係していることがあります。 原因によって治療法が大きく異なります。
主な原因となる病気
過敏性腸症候群(IBS:特に下痢型)
炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)
慢性膵炎(脂肪の消化吸収障害による脂肪便)
甲状腺機能亢進症
吸収不良症候群(セリアック病など)
薬剤性下痢(抗生物質、降圧薬、制酸薬など)
アルコール多飲
ストレス・自律神経の乱れ
糖尿病性神経障害に伴う下痢
大腸がん・大腸ポリープ
放射線性腸炎(放射線治療後)
💬 受診の目安
次のような場合は、できるだけ早めに受診してください。
下痢が3日以上続く
発熱・血便・強い腹痛を伴う
脱水症状(尿が減る、口の渇き、だるさ)がある
体重が減ってきた
長期間、繰り返す下痢がある
過敏性腸症候群
過敏性腸症候群には下痢型・混合型・便秘型がありますが、 消化管運動調整薬(モサプリド、トリメブチンなど)やポリカルボフィル、ラモセトロン塩酸塩錠(イリボー)のほか漢方薬(半夏瀉心湯、五苓散、大建中湯、小建中湯、桂枝加芍薬湯など)や抗不安剤 を適宜使用します。 病気の原因を知るためには家族歴・生活習慣・職業習慣・運動習慣・喫煙や飲酒歴などを詳しくお聞きすることが大切と考えています。その上で診察・検査をお勧めし、薬を選択していきます。